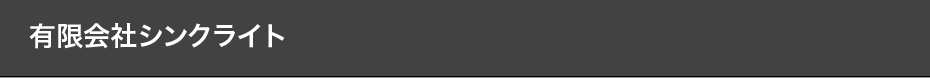
サベヤーと日本の咬合器
サベヤー
従来、部分床義歯を製作する際、クラスプの位置は目測で決定していた。しかし、術者の経験によるところが大きく、出来上がった義歯のクラスプが口腔内でつかえてしまい、装着できないことも少なくなかった。
そこで、術者の“長年の勘”によらずにクラスプの位置を決定することができるよう開発されたのがサベヤーである。
サベヤーの使用目的は主に
・義歯の着脱方向の決定
・鉤歯や歯肉部へのサベイラインの描記
・アンダーカット量の計測とクラスプ先端位置の決定
・鉤歯のブロックアウト部のワックスの削除
の4つであり、機種は以下の3種のほか、振り子型と呼ばれるものがある。
・アームが固定式で雲台が可動式のタイプ
・アームが可動式で雲台が固定式のタイプ
・アーム、雲台ともに可動式のタイプ

日本補綴歯科学会会長などを務めた堀江銈一氏が考案した
サベヤー

フリコ式のサベヤー
咬合器
ヒトの機能を機械的に表現しようとする思想は16世紀のフランスの生理学者ラ・メトリーの『人間機械論』(1747年)に始まったとされる。
現在、歯科補綴治療は主に間接法で進められ、顎運動あるいは顎位を口腔外で再現し、生体に調和した補綴物の製作を目指して、咬合器によって上下顎部の機能を機械的に再現しようとする。われわれ歯科医療従事者の先達は、咬合器と生体の動きの関連性の解明に長い時間を費やし、臨床の進歩に貢献してきた。
咬合器の開発は、主に欧米で進められたのであるが、ここでは、日本人(故人)が考案してきた咬合器について供覧する。
現在、歯科補綴治療は主に間接法で進められ、顎運動あるいは顎位を口腔外で再現し、生体に調和した補綴物の製作を目指して、咬合器によって上下顎部の機能を機械的に再現しようとする。われわれ歯科医療従事者の先達は、咬合器と生体の動きの関連性の解明に長い時間を費やし、臨床の進歩に貢献してきた。
咬合器の開発は、主に欧米で進められたのであるが、ここでは、日本人(故人)が考案してきた咬合器について供覧する。
 中原式下顎運動性咬合器(1916年) 日本歯科医学専門学校(現・日本歯科大学)の創始者である中原市五郎氏は1914年に半調節節性の咬合器(中原式咬合器)を考案した。その後、Gysiとの意見交換の末、本製品を完成させた。 |
 矢崎式咀嚼運動器(1930年) 矢崎正方氏によって開発された。咬合器ではなく「咀嚼運動器」と命名したのは、矢崎氏が提唱した咀嚼運動理論および咬頭展開角説に基づく器材だからである。(田端義雄氏[埼玉県本庄市/田端歯科医院]所蔵) |
|
 沖野式咬合器(1936年) 日本人の頭蓋や顎の解剖的計測値などに基づいて沖野節三氏が考案した咬合器。本製品発表後も沖野氏の臨床成果を反映した改良型が製作された。 |
 坪根式咬合器(1949年) 総義歯用の咬合器として坪根政治氏により開発された。その後、坪根氏は1953年に間接部の一部 を改良したTypeⅡを発表。1966年には間接部、切歯指導部および顔弓の一部を改良したTypeⅢを発表した。(阿部羅直明氏[北海道釧路市/エヌ・エ・デンタルラボセンター]所蔵) |
|
 堀江式咬合器(1958年) Gysiの下顎運動理論に基づいて堀江銈一氏が考案した咬合器。顆路指導部の中にスプリングが取り付けられており、自由運動を行う付属の堀江式リッジ・サベヤーによって石膏模型に記入した正中線を咬合器に正中に一致させることにより、咬合器上に正中線を再現できる。 |
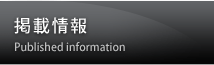
- 歯科技工師の始まり
- 歯科機械の始祖
- 蒸和釜とゴム床義歯
- エンジン
- レーズとロール
- 木冠と金冠
- 金冠制作のための小物類
- 鋳造法に用いる器材類
- 陶材と陶歯
- 陶材とポーセレンファーネス
- 硬質レジン
- サベヤーと日本の咬合器
運営会社
有限会社 シンクライト
〒350-1302 埼玉県狭山市東三ツ木5-28
TEL:04-2953-6830
